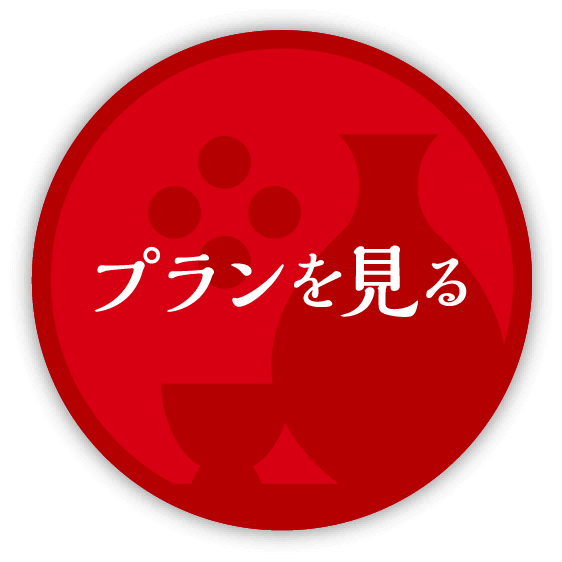極小蔵が生み出す“幻の酒”とは?
「もしかしたら、“日本一小さい蔵”かもしれません」
白壁のシンプルな蔵を前に山口佳男社長はそう話してくれました。中の広さは60坪ほど。そこから事務所スペースや製品置き場を差し引いた約45坪で「会州一」は醸されています。蔵人は季節ごとの手伝いを除けば、山口社長と奥様のゆり子さん、杜氏の櫻井光治さんらわずか4名。造られるお酒の本数も限られ、さらに内9割は福島県内でしか出回らないと言いますから“幻の酒”と呼ばれるのもうなずけます。
「売る方としてはそう言われるのは辛いですよ(笑)。でも顔の見えない営業はしたくないのと、売り先を増やしても供給量が追いつかないので。それでも多くの人に名前くらいは知ってほしいという思いはありますね」
「会州一」が“幻の酒”なのは、なかなか手に入らない希少さばかりではありません。「会津で一番の酒」という銘柄の由来のとおり、味の良さにも定評があるから。戦前から鑑評会(当時は品評会)で好成績を誇り、金賞受賞の回数は県内でも指折り。つい先日も福島県春季鑑評会・吟醸酒の部で見事金賞に輝きました。
「造る以上はちゃんとした酒、当たり前じゃない酒にし」
と語る山口社長。その決意の裏には、10年前の苦い経験がありました。

逆境に打ち勝ち、蔵人一丸となった再生劇
そもそも山口家は、名君・保科正之とともに会津に入り、酒造りを始めたという歴史のある蔵元。かつては1500坪の広大な敷地で普通酒をメインに製造していたと言います。
しかし、別事業の失敗から2006年に休業。一時は廃業も囁かれましたが、周囲の勧めもあり現在のかたちで復活しました。酒蔵の構造を知らない建築士に代わり、自ら図面を引いて設計したのは杜氏の櫻井さん。
「今考えるとよくやったなあ」と笑いますが、大変な日々はその後も続きます。休業していたことでマイナスイメージがつき、試飲会に行っても誰も来てくれなかったり、セールス先で門前払いされることもしばしば。そんな社長の姿を見て、「まだ会州一はなくなってはいない、なんとかしなくちゃ」と、櫻井さんも夢中で酒造りに励みました。
そして復活から3年後、県の鑑評会で最高賞となる知事賞がもたらされたのです。 「まあ、いい経験だったのかな。あの時間がなければ気づかなかったことがたくさんありました。再開した当初と今はお酒の中身も売り方もずいぶん違います。普通の蔵は13、4か月先まで計算して仕込みますが、うちは10か月で売り切るのが理想。貯蔵スペースもほとんどないので、完売が続くようじゃないとダメなんです。残して品質を落としてもいいことはありませんから」

今年は復活してちょうど10年の節目。会津一古い蔵元は、会津一小さくて新しい蔵として再生を果たし、新たな時を刻んでいます。
最後に「まだ自分で100%満足と言える酒はできていませんが、それでもお客さんにおいしいと言っていただけるのは幸せ。もっとおいしいものを造ろうと自分を向上させることができます。今はとにかく飲んでもらえることがありがたい。感謝の気持ちの中で酒を造っています」と、率直な思いを話してくださった櫻井さん。
そこに山口社長の覚悟が重なります。 「小さいからこそ、お客さんのニーズに応えたり、工夫できることを強みに自信を持って売っています。それが私の責任。売り切らないと杜氏に怒られるんですよ。 “社長、売り方が悪い!”って(笑)」 苦しい時をともに戦ったからこそ、言いたいことを言い合える信頼感。そして蔵の中の風通しの良さ。それもまた「会州一」のおいしさの秘訣に思えてなりません。
ふたりのやり取りをいつも見守っているという山口社長の奥様・ゆり子さんは、「こう見えて“最強コンビ”なんですよ」とこっそり教えてくれました。ここでしか生まれない味を武器に、「会州一」は日本酒ファンを魅了し続けます。