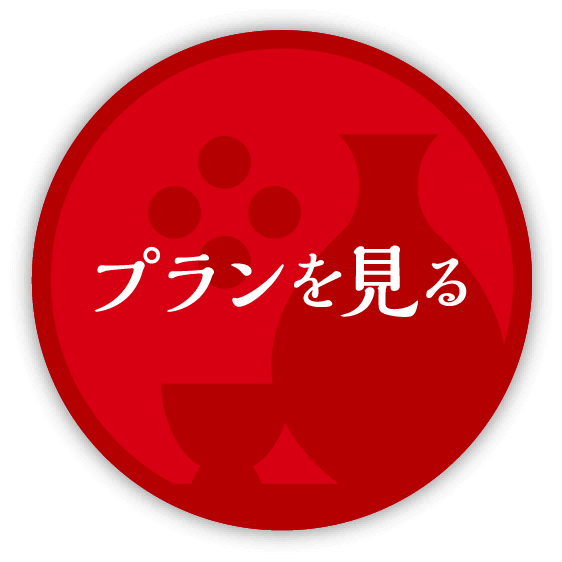酒造りへ情熱が 独自の味わいを生む
会津のお酒といえば口当たりが優しく甘みがあり、どこまでも余韻が続く、いわゆる「芳醇旨口」系。 しかし、その中にありながら独特の辛さ・キレの良さを活かした酒造りを追求しているのが辰泉酒造です。
現在、蔵を率いるのは、4代目で製造責任者の新城壯一さん。「確かに会津のスタンダードとはちょっと違うかもしれませんね」と、その理由を話してくれました。
「ベースにあるのは2011年まで30年以上にわたって来てくれていた南部杜氏さんの作り上げた味です。私も7年ほど教えてもらいながら一緒に造りました。今はそれを引き継ぎながら、新しい味わいや商品開発に挑戦しているところです」
辰泉酒造の創業は明治10年。古くから酒造業が盛んだった会津においては比較的新しい蔵でもあります。名前の由来は、「白鹿」で有名な灘の辰馬本家に初代が勉強に行った縁でと伝えられますが、詳細は不明だそう。
今では大事な“辰”の字は、瓶のキャップ部分や季節限定シリーズのラベルに描かれたかわいらしいモチーフとして存在感を放っています。 代表の新城さんが蔵に戻ったのは30代も後半に差し掛かったころでした。
首都圏の大学に進学し、そのまま電機メーカーへ就職。蔵を継ごうという意識は特段なかったと言います。 「酒蔵に生まれたとは言え、日本酒を意識したことはありませんでした。お酒の中のいちカテゴリーで、しかもあんまりおいしくないというようなイメージでしたね(笑)。でも、仕事で会食の機会が増え、おいしい食事においしいお酒を合わせる楽しみを知ってから見る目が変わりました。日本酒は実はおいしいんだ! って。
何年か葛藤はありましたが、私がやらないと廃業してしまうこと、やはりなくすのは忍びないなと思えたことで覚悟が決まりました」 マリアージュの可能性から日本酒に目覚めたという新城さん。文字通り、ゼロからの酒造りとなりましたが、持ち前の実験精神とものづくりへの探究心も相まってその魅力に引き込まれて行ったそう。
「酒造りそのものはとてもおもしろい作業です。泡が出たり、音が出たり、毎日表情が変わる醪を見ているだけで純粋に楽しいんですよね。あとは自分でおいしいと思ったお酒を、他の人もおいしいと言ってくれたときは素直にうれしいです」
控えめな中に酒造りへの熱い情熱を感じさせる新城さんの人柄は、そのまま辛口でありながらしっかりと味がある辰泉のお酒のよう。300石と決して大きい蔵ではありませんが、根強いファンに支えられていることも頷けます。

親子2代で挑む “幻の米”復活への夢
辰泉酒造を語る上で外せないのが「京の華」にまつわる取り組み。新城さん自身も、「今の辰泉を象徴する米であり酒」と力を込めます。
そもそも「京の華」は大正時代に山形で生まれた、今でいう酒造好適米の走り。昭和の初めに会津に伝わり栽培されるようになったことで、会津の日本酒が格段にレベルアップしたと伝えられています。
しかし、この「京の華」、味の良さの一方、背が高く、収量も少なく、心白(お米の中心部)が不揃いと、さまざまな弱点を抱えており、次第に作られなくなり、ついにはこの地から姿を消してしまいます。
そこで立ち上がったのが辰泉酒造の先代。農業試験場に通って種籾の選抜から行い、地元の農家と二人三脚で米作りに挑みました。お酒が仕込める収穫量に達するまで、実に4年もの歳月を要した一大プロジェクトでした。
「会津で作った米で最高の酒を作りたいという想いがあったんだと思います。それだけ「京の華」に惚れ込んだのでしょう。その父の想いを受け継ぎ、今度は私が品質を安定させ、徐々に収量も増やしていく番。「京の華」を使っているのは今ではうちだけ。私がやらないとまたなくなってしまいますから」
自社田を持ち、米作りから携わる酒蔵こそ増えてきていますが、品種改良からとなると一筋縄ではいかないもの。それでも新城さんは「残っていくためには特化するものがなければ」と強い決意を口にします。
「「京の華」をひとつの看板にして、今までの日本酒のイメージにとらわれないものを作ってみたいですね。現代は毎日同じもの食べる人がいないのと一緒で、同じ酒だけを飲み続けることもないはず。いろいろな食のバラエティに対応できる酒が必要なのかなと考えています」
先人の想いを受け継ぎながら、たゆまぬ努力で進化を続ける。その姿勢はまさに天に向かう龍のごとく力強く感じられました。

辰泉酒造
福島県会津若松市上町5−26
TEL:0242-22-0504
http://tatsuizumi.co.jp/